青年はぼんやりと考え事をしていた。
どうしてお正月に門松を玄関に立てるのだろうか?
何か霊的な意味があるのだろうか。仮に霊的な意味があったとしても、霊能力がない人間にとっては特に効果はないのだろう。あるいは、ただ単に風習として残っているのだろうか?
門松に“グッズの霊障”(第15話参照)がつきやすいかはわからない。けれど、毎年飾っている物であるから、どのような意味を持っているのかを確認しておく必要はあるのかもしれない。
そう思い、青年は厚着をして陰陽師の元を訪ねるのだった。
『先生、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします』
青年は深く頭を下げ、新年の挨拶を述べた。
「あけましておめでとう。今年もよろしくの」
陰陽師はいつもの柔らかい笑みを浮かべて小さくうなずいて答える。
『新年早々で恐縮ですが、今日は門松について教えていただけないでしょうか。毎年お正月には玄関に門松を飾っていますが、あれにはどのような意味があるのでしょうか?』
「なるほど、門松について聞きたいのじゃな。ちなみに、そなたは門松についてどのような認識を持っておるのかな?」
青年は腕を組み、しばらく黙考してから口を開く。
『お正月の数日間に、切った竹を数本と松の葉が一緒になった物を、自宅の玄関前に左右に立てる飾りだと思っています。それ以上のことは特に・・・』
青年は頭をかきながら答え、陰陽師は微笑みながらうなずく。
「民俗学者の柳田国男監修“民俗学辞典”(東京堂刊)に“門松”について次のように記載がある」
今は正月の飾り物のように考えられているが、本来は歳神(年末・年始に各家を訪れると信じられていたご先祖様)の依り代の一種だったらしく、そして必ずしも松と限らない場合が多い。(中略)
鳥海山・月山の周囲の村々でもカドバヤシ・カドマツタテといって、楢、椿、朴、みずきなどを山から伐ってきて立てる。山口県北部や宮崎県の山間でも松以外の木を立てる。これら多くの木を立てておく期間は一定しないが、一月七日まで、もしくは旧正月の終わるまでというのが多い。
「この本にも書かれているように、門松という名前から松を立てると思っておるじゃろうが、竹も含め、松以外の樹木でも問題ないことはわかるじゃろう?」
『たしかに、言われてみればそうですね。ごく一般的な門松であっても、門松なのに竹を使っている。門松竹といったところですね!』
青年は笑いながら言う。
「それが正しいかはともかくとして、日本では古来より“天なる神は柱のような木に降り立つ”という観念が存在しておっての」
『神様を数える場合、単位が“柱”だと聞いたことがありますが、神様は見えない存在であるとしても、木が依代だと考えれば、神様の数を数えるにあたり、神様が宿っている柱の数を数えればいいということなのですね』
「また、土木工事や建築などで工事を始める前に地鎮祭を行う際に、葉のついた竹を四本、四隅に立てるが、あの“境立て”からも木々には邪霊を寄せつけない呪力があるとも信じられていたことがわかるじゃろう」
青年は手を打って答える。
『更地でよく見かけるやつですね。あれも竹を使っているわけですから、神様の依り代として松にこだわる必要はないということがわかるわけなのですね』
青年は納得顔で呟き、陰陽師は微笑みながらうなずく。
「これらの例を見てもわかるように、門松の“マツ”と松は必ずしもイコールではないということじゃ」
『なるほど! でも、そうなると、なぜ門松という言葉なのでしょうか?』
「松という漢字は実は当て字で、エジプトの物神柱“マシャ”がなまって日本語でいう“マツ”になったのじゃよ」
青年は目を見張り、前のめりになって答える。
『“マツ”が“マシャ”? しかも、エジプトが起源ですか? 僕はてっきり日本固有の風習だとばかり思い込んでいました』
陰陽師は、青年の言葉に、ゆっくりうなずく。
「エジプトの文化が東方へと移動していった経緯については別の機会にゆっくり話すとして、エジプトには物神柱と呼ばれる神が四つおり、その一つである梟神マシャがインドを経由した際にインドの神様として日本に伝わったものなのじゃ。さらに言えば、東北地方で“梵天”と呼ばれている神も、元を正せば、この梟神マシャのこととなる」
『なん・・・ですと。日本は世界の文化のルーツだと思っていましたが、文化の終着地点だったのですね・・・』
驚きに目を見張る青年。陰陽師は紙に文字を書きながら口を開く。
「それだけではないぞ。たとえば、纏(まとい)じゃが、 これなぞも“マシャ”の屈折語である“ヴァッタ”(〔m〕vatta)が日本流になまって“マトイ”になったものなんじゃ」
青年はヴァッタ、マッタ、マット、マットイとよくわからないことを呟き、答えた。
『あの時代劇などで見かける“纏”のことでしょうか?』
いつものことながら、言葉だけは知っている青年であった。
「もちろん、江戸時代の火消しの男衆が持ち歩いていた、先端の方に飾りがついた長い棒のことじゃ」
『やっぱりそうですか! 先の方がタコのような形になった布がついている棒ですよね!』
青年は興奮気味に両手で棒を上げ下げする動きを見せる。陰陽師はそんな青年の様子を見て、小さく笑う。
『しかし、あんな長い棒を各家庭で立てるわけにもいかなかったので、短く切ってあのような形になっていったのでしょうね』
青年の言葉に一つ頷いたあとで、陰陽師は言葉を続ける。
「このマシャという言葉が地鎮祭の“境立て”の四本柱となった経緯は先ほど話した通りじゃが、他にも大相撲の土俵の四隅に立っている四本柱も同様の起源を持つ」
『えっ、あの大相撲の柱もですか』
驚く青年をしり目に、陰陽師はふたたび先程の本を取り上げた。
「今までに説明したことを踏まえた上で、“民俗学辞典”の次の解説に耳を傾けるとよい」
神の依り代である“柱”を立てる場所は、家の前の庭もあるし、屋内もあり、家の門の前とは限られていない。
「つまり、門松の“カド”は、必ずしも“門”とイコールではないことがわかるかの?」
『なんとなくわかります。そうなると、なんだか鯉のぼりや七夕の笹も似たような物なのではないかと思えてきます』
「それらについてはまた別の機会に話すとして、話を先に進めると」
陰陽師は再び紙に文字を書いていく。青年は食い入るようにその文字を見つめる。
「梟神柱は古代インドへ渡り、古語(梵字)で“ガダー”(gadā)と呼ばれるようになるのじゃが、これも処々の状況より“カド”となまったとも考えることができる」
青年はまた、ガダー、ガダ、ガド、カドなどと呟いた。
『口に出してみるとなんとなくわかります』
「それ故、門松の“カド”や“マツ”は、文字通りの門や松ではなく、梟神のことを示したということになるわけじゃ」
『なるほど。門松という漢字は当て字でしかなく、本当は松でなくても、門のように二本でなくても、玄関前になくても、問題はないわけなのですね!』
青年は納得した顔で何度もうなずいて見せる。陰陽師は満足そうに微笑んで首肯する。
「さらに興味深い事実として、“民俗学辞典”に以下ように記載されておるように、我が国には松を能動的に使わない地方というものが存在しておるのじゃ」
祖先が戦に敗れて落ち延びたのが正月だからといった種類の伝承をもって門松を飾らない家例の旧家もある。京都でも宮中を始め貴族の家々には門松飾りがなかった。
『ここで言う“戦で敗れた祖先”とは日本人のことだと思いますが、いかがでしょうか?』
陰陽師は首を左右に振って答える。
「いや、ここでいう“戦で敗れた祖先”とは朝鮮半島の人々のことなのじゃよ。“マシャ”という言葉が遠いエジプトから島国である日本に伝わってくるためには必ず海を渡らねばならぬ。宗教や文化というのは、必ず人と共に移動しておるわけじゃからの」
『なるほど。弥生時代に朝鮮半島から大勢の人が日本に渡海してきたことは勉強しましたが、彼らはもともと日本で生活していた縄文人とは別種の人間だったのですね・・・』
「うむ。縄文人は、今でいうアイヌや琉球民族といった、迫害されてきた人々がそのルーツで、いわゆる弥生人とは別種の民族ということができるじゃろうな」
青年は黙ったまま、納得顔で何度も頷く。
「それを裏づけるように、朝鮮半島や済州島では、松は霊城に植える霊樹であるし、朝鮮半島の西側では、捨て墓に一時的に埋葬するにあたり、死体を松の枝で覆うという習慣が存在している」
『なるほど。そのような歴史的背景を持った人々であれば、不吉なことが連想される松を避けたがったとしても別に不思議じゃありませんね』
「まあ、そういうことじゃな」
青年の言葉に、陰陽師がひとつ頷いた。
『いずれにしても、他の木々が代用されるという背景には、そんな遠い昔からの由来があったのですね。日本の文化こそが世界の文化の起源だとばかり思っていました・・・』
「じゃが、カドマツがエジプトから伝播した風習であり、今も習俗として残っていることひとつをみても、ほとんどの文化が日本で生まれ海外に伝播したと考えるよりも、その逆と考える方が、筋が通っておるじゃろうな」
青年は納得顔で何度もうなずく。陰陽師はタンブラーに注がれたお茶を飲み、続ける。
「エジプトからの道のりを説明するとあまりにも長くなってしまうから、とりあえず、身近な朝鮮半島に話を限って、説明するとじゃな」
陰陽師は日本列島と中国大陸の地図を描き始める。
「弥生文化を形成した渡来人の中心人物は、百済の王、あるいは辰王朝の宗室(王家)だったのじゃが、百済の王とは、馬韓、弁辰のかなりの部分を支配する辰王でもあった。そんな彼らの一部が、勢力争いに敗れる度に、様々な文化を携え日本に移動してきたわけじゃな」
陰陽師は説明しながら地図に国名を記していく。青年は地図を眺めながら口を開く。
『日本の文化が朝鮮半島から伝わってきたのはわかりました。それでは、朝鮮半島の文化はどこを起源としているのでしょうか?』
「直近では、北方騎馬民族である扶余(ふよ)族が朝鮮半島に南下してきたと言われておるが、ではその扶余族はどこから来たという話になると、シルクロードを中心とした陸路を遡る必要が出てくるじゃろうし、海路という話になると台湾、フィリピン諸島、マレー半島、そしてインド洋を越えて中東と、話は限りなく広がっていくわけじゃが、細かい話はともかく、すべての文化的ルーツが今のイラクあたり、すなわち、かつてのシュメールで誕生し、それらの文化が多数の人間を介して、今説明した経路を逆流するような形で日本に波状的に流入してきたと考えるのが妥当じゃろうな」
青年は地図を見ながらうなり声をあげ、何度もうなずく。
『とても興味深いです。ということは、日本文化のルーツを知るには古代エジプト、そしてシュメールにまで遡るのが大事なのですね』
「その通りじゃ。歴史で学習するすべてのキーワードとしては、メソポタミア文明といっても過言ではない」
『なるほど、四大文明の最初の一つであるメソポタミア文明は、エジプト文明、インダス文明、黄河文明とすべて繋がっているわけなのですね!』
やや興奮気味に話す青年を片手で制し、陰陽師は口を開く。
「もちろんじゃとも。メソポタミア文明の中でも、特にシュメール人が築き上げた文化を探ることで人類の起源に近づくことができるというわけじゃな」
『単純暗記していた歴史の用語でしたが、こうして現代の日本にも深い関わりがあると思うと、なんだかとても感慨深いです』
自分の世界に入る青年を見、陰陽師は微笑みながら頷く。
『となると、よく韓国人が“日本の物は韓国が起源ニダ!”と言うのは、あながち間違いではないといえるわけですね』
「たしかに、歴史の連続性という視点でみる限り、彼らの主張もまったくはずれているということはないだろうな」
『でも』
青年が、首を傾げつつ、言った。
『日本の文化が朝鮮半島を経由してきたことを認めたとしても、現代の日本人と韓国人とでは国民性が違う気がするのですが』
青年の言葉に、陰陽師は真顔で頷く。
「以前(第9話参照)説明したと思うが、頭の1/2の比率は、世界では2:8に対して日本人は3:7と、世界の平均値と比較すると頭が1が一割ほど多い」
『だから、日本は優等生と言うこともできる、とおっしゃいましたね』
「そのとおりじゃ」
陰陽師は、小さく頷く。
「一方、朝鮮や中国では、1/2の割合がほぼ1:9となる」
そう話す陰陽師の言葉に耳を傾けながら、青年は記憶をたどるように一点を見つめて黙考し、口を開く。
『たしか以前のお話では、頭2は狩猟民族の末裔で、物事を損得で考える傾向が強いため、結果、自己中心的な傾向が強いということだったと記憶していますが、だから韓国人は自国が優位になるような主張をする傾向が強いのでしょうか』
「半島に住む人々というのは、朝鮮半島に限らず、地続きの大国の影響を受けやすいという特徴を持っておるわけじゃから、もちろん、そう考えることも可能じゃろう。しかし、決して忘れてはならぬのは、魂は、各々属性にとって最も修行に適した国を選んで転生してくるという原則じゃ」
『つまり、日本を選んで生まれてくる人間は、修行をするにあたり日本が最適の修業の場であり、韓国や中国に生まれる人間は、それらの国が修行の場として最適であるというのですね』
「その通りじゃ。さらに言えば、同じ1/2であったとしても、程度という問題も存在する」
『つまり、1/2に枝番があり、それによって度合いが存在するわけですね』
「さらに言えば、16通りある、輪廻転生と魂の組み合わせにも、それなり以上の相違もある」
『なるほど』
「じゃから、たとえ姿形がいかに似通っていようと、同じ人間だから話せばわかる式のコミュニケーションではなく、各々別種の人間として話をする必要があるわけじゃな」
『そのあたりの話は、じゅうぶん理解しました』
陰陽師にそう答えた後で、青年は言葉を続けた。
『ところで年も明けたので、明日にでも初もうでに出かけようと思っているのですが、今お話にあった1/2という問題は、神様や寺社といったものにも当てはまるのでしょうか?』
「もちろんじゃとも。今まで説明してきたように、文明に連続性というものが存在する以上、たとえば、古事記・日本書紀に出てくるような神様も、日本古来の神様と考えるよりも、様々なルートで日本に辿り着いた民族が祭っていた神々や祖王たちと捉える方が論理的じゃと思う。よって、それらの神々も祖王たちも、また彼らが鎮座されておる神社にも、当然1と2の別が存在することとなる」
『やはり、そうなのですね。今までのお話を伺いながら、漠然とそうじゃないのと思っていましたが、ということは・・・』
小さく首を振りながら、口を開きかけた青年を、陰陽師が制した。
「そのあたりの話を説明するには、それなりの時間が必要じゃ。それには今日はちと時間が足らんようじゃな」
青年はスマートフォンに触れて時間を確認する。
『いつものことながら、もうこんな時間ですか。では、また別の機会にその話をじっくりご教授ください』
「あいわかった。寒いから風邪を引かぬようにな」
青年は席を立って深く頭を下げる。顔を上げると陰陽師が手を差し出しているのが見え、青年はその手を固く握るのだった。
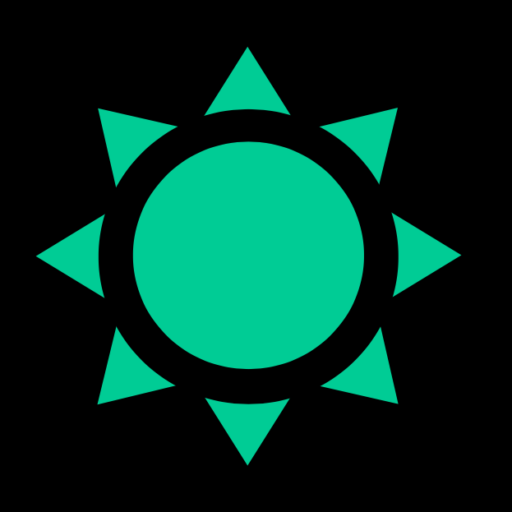
コメントを残す