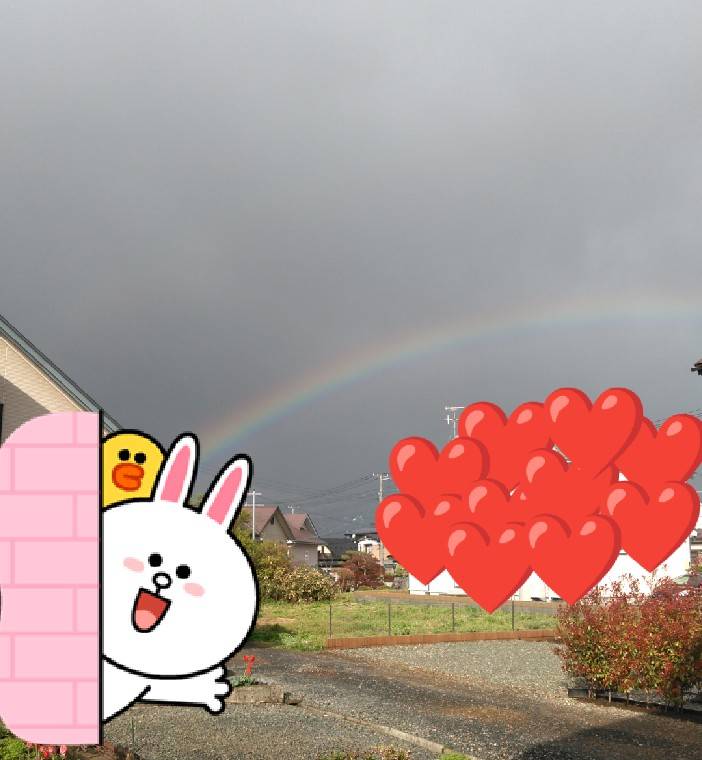もうすぐお盆の時季ですね。
もうすぐお盆の時季ですね。
- お盆でどんな用意をすればいいのか?
- きちんと決まった用意をしなければならないのか?
- ちゃんと用意しなければ、バチが当たるのではないか?
そんなお悩みを抱えているあなたにお伝えしたいことがございます。
お盆で用意すること
私が思うに、お盆で用意することは、大きく分けて二つです。
①その日に家族が食べたい料理
②玄関や家の周りに着ける電飾
なぜこの二つになるのか、説明していきます。
①その日に家族が食べたい料理
お盆に限らず、故人へのお供物として料理を用意しますが、その理由は“お盆”という言葉にあります。
柳田國男氏の書籍によりますと、
お盆の“盆”という漢字は“瓫”と書きます。
この漢字には“行器”(ホカイ)、食べ物を入れて神霊に供える器という意味があります。
そして、食べ物を供える対象である神霊には祖霊、すなわちあなたのご先祖さまの魂も含まれるようです。
つまり、ご先祖さまに食物を供えるという習俗が“お盆”には含まれているわけです。
しかしながら、よく考えればわかるように、ご先祖さまや故人は肉体を持っていないため、食物を必要としません。
ですから、わざわざご先祖さまのためにと、家族の分とは別に料理を用意する必要もありません。
よく故人がお腹を空かせてしまうから、といった話を耳にしますが、肉体がない以上、空腹、胃が空っぽになるということがありません。
仮に、故人が食べ物を必要としているなら、お供えした料理が減るはずです。
では、食べ物を供える意味がないなら、ご先祖さまに何もしなくていいのでしょうか。
お盆というイベントにおいて、せっかくなら、ご先祖さまのために何かしたい、ということでしたら、ご先祖さまを供養しようというそのお気持ちでじゅうぶんだと私は考えます。
そうは言っても、気持ちだけでなく、ご先祖さまへの感謝の気持ちを示すために、何らかの行動をしたいという方もいらっしゃると思います。
“故人がお供えした物の気を食べている”
“あの世への子孫からのお供えによって、故人に対する審判の判断基準が変わる”
という説もあるようですし。
そんなあなたは、お盆の期間に用意した料理を味わって食べてください。
一口食べて、料理が減るごとに、今、ご先祖さまと共に食事している。
そう思い、目の前の料理をお供えしつつ、家族で食事を楽しみましょう。
きっと、ご先祖さまも、しんみりと暗い雰囲気で一緒に食事をするよりも、賑やかに、明るい雰囲気で食事をすることを望んでいることでしょう。
ですから、クリスマスパーティーのように、あなたとご家族が楽しんで食べられる好物やご馳走を用意するのもいいかもしれませんね。
たとえば、こんな風にするのもよろしいかもしれません😊

<引用元:シャーマンキング>
よく、ナスとキュウリを、牛と馬に見立てて用意するという話が出てきますが、私は気にしなくていいと思っています。
というのも、お盆で元々備えられていた食材は、ナスとキュウリなどを四角く刻んだ“水の子”と呼ばれる料理でした。
ナスとキュウリだった理由は、それらはお盆の時季の旬の食材で比較的多く採れたからではないかと私は仮説を立てます。
今の時代は食べ物に恵まれ、旬を問わずに食材を選べます。
ナスとキュウリにとらわれず、ご家族で食べたい料理を食べましょう。
また、一説によりますと、ナスの牛とキュウリの馬は、農作業の際に牛や馬は貴重な労働力だったため、牛と馬を労い、感謝してナスとキュウリを見立てたそうです。
この説が正しいなら、ナスの牛とキュウリの馬はご先祖さまのためではないこともお分かりかと思います。
よって、ご先祖さまがナスの牛やキュウリの馬に乗るという話も、後の時代になってから創作されたものでしょう。
よく、ご先祖さまが家に帰ってくる時は牛に乗ってのんびりと、一方、家からあの世に戻る時は馬で急いでと聞きます。
なぜ、ご先祖さまを急いで帰らせるかというと、餓鬼などの良からぬ存在がご先祖さまと一緒に着いてくるからだそうです。
日頃から施餓鬼をし、しかも確実に餓鬼たちがあの世に戻れているなら、心配する必要はありません。
ですが、良からぬ存在に対して有効な手続きを行えていないから、そうした見えない存在に対して恐れを感じているのでしょう。
余談ですが、クリスマスといえばチキンですが、元々は牛や豚を食べていたようです。
ところが、アメリカ大陸に進出した当時のヨーロッパの人々は、現地で牛や豚を飼育することが難しかったようで、その代わりとして、アメリカ大陸に多くいた七面鳥の肉を代用したという説があります。
つまり、キリストの誕生日を祝うためのご馳走であれば、牛や豚に限らず、七面鳥でも良かったのでしょう。
厳密な決まりではなく、臨機応変に変えても良さそうです。
ですから、日本固有のイベントであるお盆に用意する料理も気にせず、クリスマスのようにご馳走や家族が食べたい料理を用意するのがよろしいかと思います。
②玄関やベランダに着ける電飾
先に結論をお伝えしますと、これはなくてもいいです。
というのも、大昔のようにわざわざ玄関の前に“迎え火“として火を焚かなくても、電気のおかげで現代ではほとんどの家は外灯も室内も明るく、家の場所がわかるからです。
ちなみに、家の門口に火を焚くことをホーカイと呼ぶようで、①の行器(ホカイ)と音がほぼ同じです。
ただし、どの家にも明かりがあり、ご先祖さまにとって他の家と区別がつかないのではないか?と心配する方には、他の家と区別するために、クリスマスのようにライトアップするとよろしいかと思います。
そうは言っても、我が家は昔からの慣習通りに準備したいと考える方がいらっしゃるかもしれません。
実際のところ、玄関の前に迎え火として置かれていた松明は1230年頃、鎌倉時代から、高灯籠になりました。
同時に、その頃から、提灯や灯籠、墓参りの風習が始まったとも言われています。
高灯籠とは、長い竿の先端に提灯を置いて灯す物で、少し形が変わりますが、お盆の時期には“灯籠流し”が開催されています。
ちなみに、ネット通販でも買えますし、電気式です。
つまり、時代と共にやり方や道具が変わっていますので、必ずしも松明を用意しなくてもよろしいかと思います。
そうした形式にこだわることも大事ですが、より大事なことはお盆祭りをイベントとして楽しむことだと私は考えます。

こちらの画像は、日本一の灯籠流しと言われている、“永平寺大灯籠流し”の画像です。
この灯籠流しには、お盆の時期にやってきたご先祖さまを送り返したり、水死者や無縁仏を供養する意味があると言われています。
言い換えると、迎え火に対する”送り火“としての役割があると思われます。
余談ですが、大雑把に言って死者の魂を川に流す理由は、”ニライカナイ“と関係があると私は考えております。
”ニライカナイ“とは、海中や海の向こうにあの世があるという考え方です。
川に灯篭を流すのは、いずれ川から海に、そしていずれは海の向こうに灯篭とともに死者の魂がたどり着くからと昔の人は考えていたのでしょう。
川に流す理由として、他に考えられるのは、火葬ではなく風葬が主であった時代では、死体を川に捨てて放置していました。
現代のインドでも、遺体をガンジス川に流す、水葬が行われているそうです。
ひょっとしたら、川=死者が還る場所、というイメージがあったのかもしれません。
地域によっては、迎え火と送り火をともに家の前に設置していたり、送り火は村人全員が海岸に行って火をつけたりと、やり方が異なります。
この背景には、送り火が何らかの要因で村に火災を招いたため、安全のために海岸で行うようになったという説もあります。
つまり、送り火の場所はどこでもいいと考えられるわけです。
ちなみに、現代では、灯籠流しが環境汚染につながるという理由から、やめてしまった地域もあるようです。
灯籠流しに、本当に死者の魂を供養する効果があるなら、灯籠流しをやめたことで何らかの不幸なできごとが起きたかもしれませんし、環境汚染を考慮した上でも断行すべきではないかと思われます。
つまり、環境汚染という科学的な理由を優先してやめてしまう行為なら、そもそも灯籠流しにはそこまで霊的な効果があるとは言い難いと、私は考えました。
それなら、灯篭を流さずに、お盆の時期に灯篭を家族で自作するか、購入して用意するのもよろしいでしょう。
そうした理由も考慮して、多くの家庭にあると思われる、クリスマスツリーや、電飾をお盆でも使うことを推しました。
クリスマスツリーや電飾を、年に一度だけでなく、お盆でも使って楽しんでみてはいかがでしょうか?
もちろん、お盆=提灯(和風の明かり)だと認識している人が多いと思いますので、クリスマスツリーを出すのは室内だけにし、ベランダなどには、トナカイやサンタクロースといったクリスマスを想起させる物を外した電飾で明るくするのが無難でしょうか。
ここまで読んだあなたは、お盆に対するハードルが下がり、さっそくお盆の準備に取り掛かろうと思ったことでしょう。
残るは、いつお盆をするか、ですね。
お盆の期間は諸説ありますが、一番早い始まりの日が7/1で、終わりの日が8/24のようです。
この期間内でも、昔の太陰暦を意識するなら7/15、現代の太陽暦を意識するなら今年は8/13〜15です。
この三日間を表盆と呼ぶのに対し、8/24は裏盆と呼ばれています。
7/1〜8/24まで電飾を出すのは長過ぎる!と感じる方は、お好きな日数に短縮すればよろしいかと思います。
世間に合わせるなら8/13〜8/15(と8/24)に。
元々の由来に合わせるなら7/15がよろしいかと思います。
お盆の由来
なぜ、お盆は7月15日なのでしょうか。
実は、お盆の由来は、日本の民族信仰と仏教という、二つの説があります。
過去の日本には、1月と7月の初春と初秋の最初に祖霊が訪れてくるという民族信仰があります。
ちなみに、旧暦の1/15も7/15も満月の夜になるそうです。
そして、この“瓫”は、食べ物を入れて神霊に供える器という意味を持つ、“ホトキ”の言葉の一つです。
この神霊には祖霊、すなわちあなたのご先祖さまの魂も含まれていますので、日本の民族信仰におけるお盆の目的は、“先祖供養”と言えるでしょう。
また、お盆の“盆”は“盂蘭盆経(うらぼんきょう)”という仏教の経典の“盆”から来ているという説があります。
そして、この盂蘭盆経に初秋の満月の日付(7/15)が書いてあり、日本の民族信仰と仏教の日付が重なっています。
盂蘭盆経の内容は、ブッダの弟子の一人が、死してなお飢えて苦しんでいる彼の母親を助けようと、食べ物を捧げたというものです。
彼の供養が功を奏したからか、彼の母親は無事に成仏することができ、彼はブッダに“先祖に対して食べ物を供えることは、ブッダの弟子なら誰でもすべきかと問うたところ、YESと答えたそうです。
この死後も飢えている人物に食べ物を備えて供養することを施餓鬼と言います。
なお、ブッダは、
“妻子も、父母も、財宝も穀物も、親族やそのほかあるゆる欲望までも、すべて捨てて、犀の角のようにただ独り歩め
ブッダのことばースッタニパーターの第一 蛇の章の三:犀の角
と述べていたようです。
それなのに、親の供養を勧める旨の記載があることは矛盾していると私は感じました。
ちなみに、盂蘭盆経は、5〜6世紀に中国で成立した偽経であり、儒教の孝行倫理が影響を受けて創作されたという説があります。
もちろん、親を大切にする教えは大事だと思いますが、盂蘭盆経がブッダの教えに沿っているとは言いがたいです。
また、そもそも、この施餓鬼は時季を問わずに行われているため、お盆にやる必要はないものです。
お盆の時期にお坊さんを呼んで読経をあげてもらう習慣があるようですが、お盆と仏教が関係ないと感じる理由があります。
それは、“盆棚”の存在からわかります。
盆棚とは、お盆の時期に先祖供養をするための棚で、仏壇とは別に、お盆の時期に作る物です。
もともと自宅に仏壇があるなら、仏壇で一緒に供養すれば盆棚を作る必要はないと思います。
さらに、先祖供養するのに盆棚が必要なら、盆棚を設置していないお盆以外の時期にお坊さんが仏壇に読経しても、先祖供養としての役割を果たしていると言えるのでしょうか。
このことから、必ずしもお盆にお坊さんを呼ぶ必要はないことがわかります。
さらに言うと、村に寺院が設置されていなかった昔は、村人が読経していたそうです。
村人が読経していたということは、読経はお坊さんの専売特許ではなく、親族や家族が読経しても構わないのです。
読経は練習すれば誰でも読めます。
赤の他人であるお坊さんよりも、子孫に読経してもらった方が、ご先祖さまは喜んでくれると思います。
お盆でわたしたちがすべきこと
ここまで読んでくださったあなたは、お盆で準備することには厳密な決まりや効果がないことがおわかりかと思います。
ただし、儀式的な行為に霊的な意味はなくとも、その行為を行おうとする目的があることはじゅうぶんに理解されていると思います。
その目的とは、大きく分けて二つあります。
①先祖供養
②無縁仏・餓鬼に対する供養
これらに共通して行うべきことは、“地縛霊の救霊”となります。
人は死後、魂が肉体から離れた後に、あの世へ通じる扉を通ってあの世に戻り、この世の時間で28年間かけ、あの世で今世の振り返りと、来世の課題を設定し、再びこの世に転生するという説があります。
しかしながら、この世に何らかの未練があり、あの世へ通じる扉を通らないでいると、その扉が閉じてしまいます。
しかも、一度閉じたその扉は、自力で開けることができないそうです。
そうなると、肉体から離れた魂はあの世へ戻れず、この世をさまよい続ける地縛霊と化します。
地縛霊化したあなたのご先祖さまは、子孫であるあなたに救いを求めます。
彼ら/彼女らは霊感があり、見えない存在に対する理解がある、霊的に頼りになる子孫を選んでいます。
子孫がいない人物が地縛霊化した場合、どうなるのでしょうか。
そうした地縛霊たちのことを、無縁仏・餓鬼として説明いたします。
ちなみに、肉体を持たない霊は食べ物を必要としないことはさきほど触れましたので、地縛霊にとって共通している、唯一にして最大の願いが、“あの世に戻ること”です。
先ほどの地縛霊の話で、霊的に頼りになる子孫に救いを求める、とお伝えしました。
ただ、現代のように食べ物に恵まれ、平和な世の中ではなかった時代、たとえば戦国時代では、流行病で命を落としたり、餓死したり、戦で若くして亡くなったことで子孫がいなかった人物がいることは、想像に難くないと思います。
こうした、子孫を持てなかった地縛霊は、救いを求める子孫がいないため、生前に縁があった“土地”にかかることになります。
お盆では、自宅に帰ってくるご先祖さまと一緒に、餓鬼などのよからぬ存在がついて来るという説があります。
そのためか、送り火を用意したり、きゅうりを馬に見立て、早く帰ってもらおうとするのは、餓鬼にも帰ってほしいという意図があったと思われます。
実際、怪奇現象が起きる建物の土地には地縛霊がかかっていることが多く、救霊の神事を依頼した後は、怪奇現象が止まったとのお声がありました。
昔の人々も怪奇現象を体験し、餓鬼・無縁仏である地縛霊からの被害を受けていたのかもしれません。
では、ご先祖、無縁仏、餓鬼を問わず、地縛霊にあの世に戻っていただくにはどうしたらいいのでしょうか。
あの世へ通じる扉を開けられるのは、優れた霊能力を持つ人物だけです。
その霊能力者/陰陽師の力を借りることで、地縛霊は死後からずっと続く長年の苦しみから解放されます。
霊能力にはピンからキリまであり、地縛霊を確実にあの世に戻せるのは、偉人で言うと、ブッダやキリストや安倍晴明クラスの能力者です。
また、霊能力の強さは生まれつき決まっており、修行などによって後天的に強くすることはできないという説があります。
お墓で幽霊を見かけることが多いと耳にすることがあると思われます。
修行によって霊能力を強くできるなら、修行したお坊さんが地縛霊をあの世に送れることから、お墓で幽霊をみかけることはないはずです。
このことは、神社で怪奇現象が起こることも同様の理由でしょう。
つまり、お坊さんや神主は修行をしているからと言って霊能力を持っているとはかぎりませんし、彼らの中から稀有な霊能力者を見つけることは至難と思われます。
余談ですが、霊感がある人物は全人口の3割という説があります。
霊感がない7割の人物は、たとえば、私が氣を送っても何も感じません。
見えない存在は信じない、科学万能主義といった傾向を持つ人物が多いです。
そうした7割の人物は、霊という存在を信じませんから、当然、ご先祖さまが地縛霊化して苦しんでいることを考えもしませんし、霊能力者/陰陽師に関わろうとしないか、何らかの縁があっても、まともに話を聞こうとしないことが多いでしょう。
ですから、ここまで読んでくださったあなたは、霊などの見えない存在についてある程度の理解があり、ひょっとしたら霊感をお持ちかもしれません。
”出逢いは必然”。
つまり、この”出逢い”には、人同士に限らず、このランディングページと、今こうして訪れているあなたとの”出逢い”も必然のようです。
ひょっとしたら、地縛霊化しているあなたのご先祖さまが、あなたに救いを求めてこのランディングページに導いてくださったかもしれません。
本当の意味で先祖供養をしたい、無縁仏や餓鬼にも供養したいとお考えの、心優しいあなたは、一度ご相談ください。
そして、本当の意味でご先祖さまが救われているうえで、お盆の儀式をお祭りのように楽しんでいただけたら幸甚に存じます。
ご先祖や地縛霊を供養したいと頭によぎったあなたは、ぜひ
コチラからお問い合わせください。




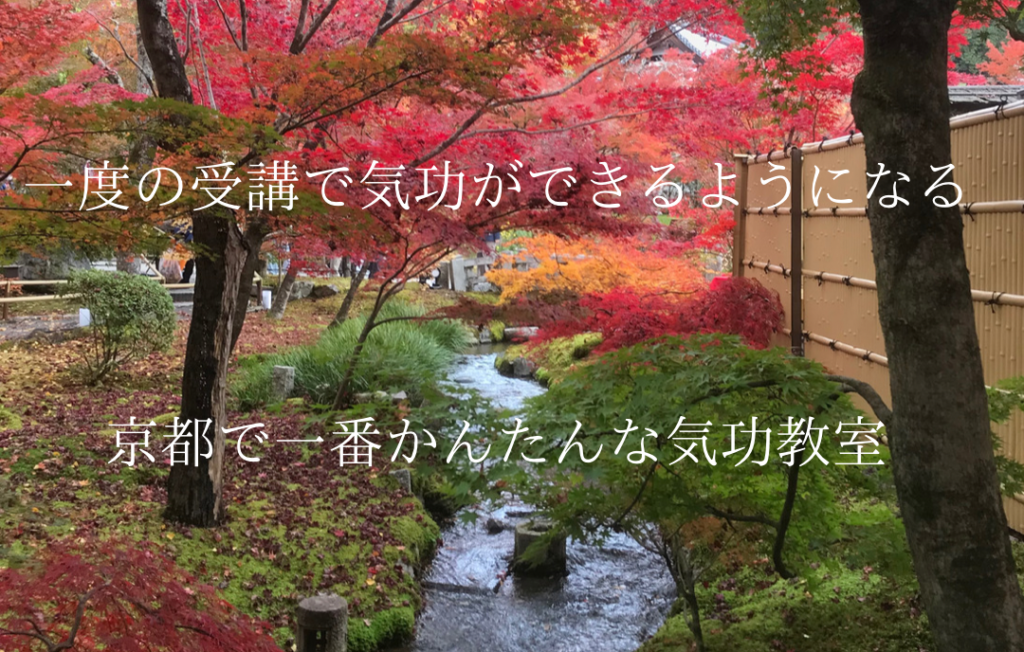

 もうすぐお盆の時季ですね。
もうすぐお盆の時季ですね。